| event/2009/spring ●水辺●エコ講習会●ソーラー●枝豆 |
| ●水辺の楽校・渡良瀬遊水地調査/国交省・野木町・野木山想会共催 |
 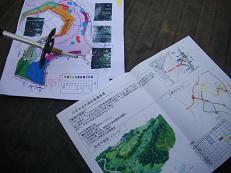 渡良瀬遊水地で野木町主催の、水辺の楽行(水辺のがっこう)の調査に参加しました。参加者は総勢27名。国土交通省担当、野木町役場、地元住民、市民グループ、わたしたち地元山岳部【野木山想会】自然保護部。   野木町の【水辺のがっこう】は渡良瀬遊水地の一角を自然の景観をなるべくそのまま生かし町民の憩いの場所と同時に、動植物の生育場所、ビオトープの形成の学びの場を提供することが目的です。概ねの構想は国交省と野木町で出来ているが、細かい意見を取り入れ、完成後の管理、メンテを含め町民参加型で運営したいと言う考えである。 わたしの所属する地元山岳会【野木山想会】は日ごろから、近隣山系の清掃ハイク活動、植林活動、河川の水質調査を行っており、会の自然保護活動に期待しての出動要請でありました。   <全体> ・全体的に涸れている木はきれいに全部伐採したほうが良い、また朽ちた木も取り除く必要がある。 ・樹木を伐採する基準としては、落葉樹は除いてそのまま残す。針葉樹は原則として伐採する。 但し、針葉樹を残す場合は下の部分を枝打ちして景観を確保すればよいだろう。 ・葛の木の蔓(つる)類は樹木を枯らしている現状(寄生)から、刈り取る。 ・水の流れをよくする、特に清水が湧いている所の掃除を行う必要がある。 ・弁財天と道路の脇に生活排水が流れ、用水路確保など手立てが必要。 ・浄化センター道路のガードレール 反対側の野木城址から望むと実に景観を損ね、白色は問題だ。濃茶色などに塗り替えることが必要では。 <稲荷谷竹林地区> ・孟宗竹 鬱蒼としているので暗い、会長が話していたとおり 間引き・伐採が必要だ。 その基準について1本〜1.5本/平方メートルかどうかは専門家とこれから詰めていけばよい。 ・下草(和シュロ、アオキ等)は全部伐採してよい。 高木は残す。針葉樹を残す場合は枝打ちを。 <野木城址> ・現在は、小笹が生い茂っているので堤防が保全されている、土が柔らかいので人が斜面に入ると盛土が壊れていくと感じた。斜面の盛土に対して保全の確保が必要だと感じた。 ・城址のあぜ道は桜の植樹をしたら親しまれる景観になるだろ、しだれ桜が良いとの声が多かった。 <清水谷竹林>杏林製薬野木研究所近く ・真竹とは思えないほどの太い竹、孟宗竹と思うくらいだ。中に入ってみたが、すごいジャングルだ。 倒木でとても入れない。 あの生い茂る密度もすごい。伐採するにしても手間、伐採林の後処理と頭の痛い竹林だ。2期工事なので時間はある。地元の声、アイデアを募集し良い手段ないか検討。 <湿地の葦(ヨシ)> ・決して綺麗ではない、自然を残すのだからそのままでいいとは言えない。 野焼きができるところもあるのではないか。民家が近くにあるので慎重さが必要。野焼きなのか、刈取か専門家の意見を聞く価値はあると思う。 <蛍> ・現状の清水、清流では無理。将来蛍の生息地にして楽校の呼び物にしようと思うならば、水の確保をどうするか検討が必要だ。これはこれでプロジェクトを作っていかないと無理だろうと思った。また、井戸の水を汲み上げるモーター(小屋囲い)があったが、活用の手はあると思う。蛍の成育には農薬の影響が甚大なため周辺の環境だけでは難しいと思われ、絵に描いた餅とならないように小金井の市民グループのように十分な研究が必要。 <最後に> ・清水谷の道路付近 生活ゴミが捨てられていたので、ボランティアでクリーン作戦が必要。われわれ地元の山岳会として、ゴミ拾いの労力は惜しまないが、回収後の処理については町でキチンと片付けることが条件だ。 ・完成後のメンテナンス、これは大変だと思った。ありとあらゆる団体の協力がないと維持していけないのではないかと思った。それが地元の野木区だけに負担がかかってもいけないし、シルバー人材などの活用も考えて行政として予算計上しないとやっていけないのではないかと思う。 ・現地視察してみて、やることは一杯あるな、これは大変だなと思った。工事の範囲が何処までなのかがわからない。やりたいことを列記してみて(整理も必要) これは 国土交通省、野木町行政、これは町民(ボランティア)などの棲み分けが必要なのではないか。 ●ヨーロッパ・エコ建築実践講習会開催/下野市・生涯学習センター   ●太陽光発電事業者講習/栃木県主催・枝廣淳子特別講習会参加 ●第9回枝豆トラスト参加/下野市・環境問題を考える会主催 |