| 【日時】平成16年9月19日(日) 10:00〜JMRA主催 |
 |
午前10時倉賀野町 九品寺集合
倉賀野五郎行信の開基で、善光寺三尊像で有名 参加人数30人(東京都3人・茨城1人・高崎3人・その他) 職種 インテリア関係2人・工務店1・設計会社2人・その他 |
||
 |
午前10時30分 脇本陣外観見学 本陣とは大名や公家専用の宿泊施設・脇本陣とはその家来、 一般用の宿泊施設。 本陣は現在スーパーマーケットとなってしまいました。 |
||
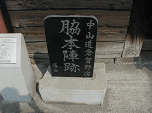 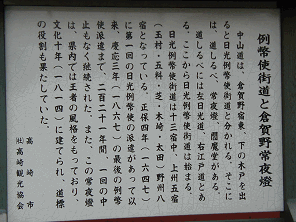 |
高崎市景観賞受賞銘板2002年受賞 高崎市が重要建築物と指定し所有者と市民、行政が協力し保全活用にあたる。 |
||
 |
午前11時 旧平井家見学 江戸期建造の長屋門が今でも残りそこをぬけると 母屋があります。写真奥は馬屋、手前物置 現在リサイクル中(90%終了)ですが今後は老人介 護施設へと変る。ご老人の精神的配慮から現代建築ではなく日本古来の住環境が一番最適と考え今回の再生工事となったそうです。 |
||
 |
平井家玄関 玄関土に点圧をかけるだけの簡単な施工 写真は点圧かけた土間の上に塩化カルシウムを引き詰めているところです え!?塩化カルシウムは凍結防止であまり人体によくないと思っていたが、乾燥材の役割もあり土間の調湿作用と経年変化で黒くなり風合いがでるとのこと。 |
||
 |
平井家 居間 リサイクルはほぼ終了 間仕切壁の撤去・木部塗装(炭を顔料にした油)及び床補強。 奥では近隣の方が障子紙を張替えていました |
||
 |
平井家 浴室 壁はすべてタイルはりですが天井は松、床はヒノキを使用。 もちろん浴室換気乾燥暖房機(ヒートショックを配慮してとのこと)を完備していました。 素足で侵入(本当は見学不可の部分)してみましたが木の質感は最高です。 当日の気温は残暑のためか30度以上ありましたが室内は暑くなかったのはその建物構造、使用材料のおかげかもしれません。 |
||
 |
|||
 |
ヒノキを使用していますが、驚いたのは防腐材等は一切使用せず入浴後上の写真の様に床板を上げ、浴室乾燥機を使用すれば長持ちするとのこと。 | ||
 |
12時 閻魔灯見学 旧中山道と日光例幣道との分岐点に建立され、ここにロウソクが燈され標識の役目をしていた。 当時この場所は京の朝廷から金の例幣を託された例幣使が日光へ行くための参拝道として利用 戦前は如来堂とよばれていたらしい。 |
||
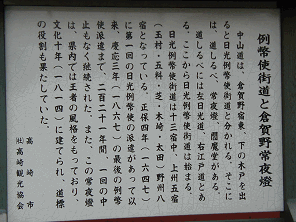 |
|||
 |
12時30分吉野邸 見学及び昼食 明治期建造の建物で屋号が「汁屋」 建物正面には連子格子が美しく残る |
||
 |
吉野邸玄関 玄関を入ると土間の真ん中に石がある 土間から座敷の高さが40cm前後あり当時はこれを踏み台として利用していたとのこと 写真右側は当時の囲炉裏がそのまま残っていました。 |
||
 |
|||
 |
吉野家にて郷土料理をいただく。 1)焼饅頭 非常に甘かった。 2)うどん 地元の材料でつくる味噌味のうどん 3)その他 金平ゴボウ、野菜漬物等吉野さん庭 で採れたものばかり。お土産でカリントウをいただきました。 |
||
 |
築50年の吉野家にて記念写真。 ※吉野様談 普段は冷房を一切使用していないがやはり冬は寒いとのこと。 普段の建物修繕については、あまり気にしていない(確かに縁側の廊下は床板がはずれていた。) ただ、雪が多いので屋根のメンテナンス(漆喰、瓦)・外壁の塗補修(松ヤニ・ベンガラ等)は定期的におこなっているとのこと。 |
||
  |
|||
 |
午後2時 大山家見学 ナマコ壁を見せる明治時期建造の蔵作の商家 残念ながら外観のみの見学 この建物の裏には(伝馬制1843年幕府により大名や公家の荷物を運ぶための人足と馬を常備する制度)御伝馬人馬継立場跡があり当時の趣がそのまま残る。 午後3時 解散 |
||
今回の古民家再生リサイクル協会のイベントに参加して 地球温暖化、リサイクル、環境問題、シックハウス、アレルギー疾患など様々な問題が伝えられる現在、日本古来より先人達に守られてきた古き良きものが廃れ、忘れられようとしています。その中の一つ1400年以上の歴史ある畳は、進化させつつ慣れ親しまれた素材です。 その原料である国内いぐさが、おそらく後数年でなくなろうとしています。(現在流通しているものは中国産が90%、国内産でも染料としてマラカイトグリーンという重金属系のもので染められているもが多い)農家に後継者がいないことを意味しています。これは、いぐさ農家に限らず、ものつくりの人たち「職人・農家」も現在、伝統素材消滅、後継者不足、森林、農地荒廃など多くの問題に直面しております。 今後、環境破壊を招かない明るい社会と伝統文化を残し、伝えられることが必要と考えられます。それは、住いだけでなく衣食住すべてにおいて言えることです。これから身近な素材を上手に生かしながら、安心と癒しを通じて伝統技術や日本文化を、残し、その考えを広げなければならない、と感じました。
|
|||
| 民家再生トップへ戻る | |||