| 【日時】平成19年10月29日(火)〜30日(水) |
―屋島・「四国村」/江戸〜大正時代の四国地方の民家博物館―
山麓に広がる広大な敷地に郷土色豊かな民家が点在
「四国村」という愛称で親しまれ、香川県の観光名所として知られる「四国民家博物館」。四国各地から移築、復元された民家が山麓の広大な敷地内に点在しています。ここは、源平の時代からの歴史がある香川県高松市の南の「屋島」の山麓に昭和51年にできました。約57,500平方メートルという広大な敷地に、民家33棟を中心に、徳島の「かずら橋」や小豆島の「農村歌舞伎舞台」など四国の建築を知る上で重要な資料が沢山あります。川崎生田丘陵の「日本民家園」とスケール、内容はよく似ており丘陵地帯の豊かな自然の中に建物が点在し、元々そこにあったような佇まいです。江戸時代に建てられた「旧河野家住宅」「旧木下家住宅」など国指定重要文化財8棟、民具6500余点、県市指定文化財など充実した内容とそれらを取り囲む、四季折々の草木の表情を楽しみながら半日かけて見ました。途中には安藤忠雄設計の「四国村ギャラリー」との新旧建築美を見比べるのもいいですね。
民家の博物館「川崎民家園」の過去の取材記事
高松・瓦町〜琴電志度線・(20分程)屋島駅〜徒歩(12分程)に四国村はある。入場すぐの「かずら橋」を渡るときには足元に注意。
農村歌舞伎 土佐漆喰壁に「なまこ壁」が美しい。 干し柿が季節感を醸し出す。
左側の隠居の家は縁側からの「上がり」が低い当時のバリアフリーである。
醤油蔵と内部の土壁に柱・貫が美しい。
砂糖締め小屋と構造。牛が円周した。
土佐地方の多雨に備え漆喰建物に3段庇がつく。
タコ漁の民家。上がり口〜座敷の間に竹組の砂落としがある。 西日本の土壁は珪酸が多く関東より丈夫といわれる。
西日本には「かまど」が多い。東日本に多い「囲炉裏」は食生活より、むしろ養蚕の暖房との関係が深い。
民家の博物館「川崎民家園」の過去の取材記事
―国の特別名勝・高松・栗林公園/江戸初期の回遊式大名庭園―
天亀、天正の頃の豪族佐藤氏の手で築庭されたといわれるこの庭園は、寛永1625年ごろ、讃岐領主生駒高俊公によって南湖一帯が造園され1642年に入封した松平頼重公に引継がれました。それから約100年間、歴代藩主が修築を重ね明治維新までの間、松平家11代228年間に渡り下屋敷として使用されていました。明治4年1871年高松藩廃止、明治8年、1875年に県立公園となり一般に公開されるようになりました。国の特別名勝の庭園としては、国内最大の規模を持つ「栗林公園」。松の緑深い、紫雲山を背景とした6つの池、13もの築山を巧みに配した江戸初期の回遊式大名庭園です。地割りと石組みと木石の雅趣に富み、春は梅、夏の花菖蒲・蓮、秋のカエデ、冬の椿と四季折々の風物に恵まれます。
高松市の中心にある「栗林公園」まではJR高松駅地下で市運営の「レンタルサイクル」が非常に重宝しました。市外の観光客にも永久会員証を発行してもらえます。利用料金24時間100円も、返却場所が市内6ヶ所で可能なところも大変思いやりのある市の取り組みと言えます。流石!四国の玄関口、最大の観光都市と感じました。わたしたちの住む、栃木県には国際的観光地「日光」がありますが、是非参考にしてもらいたいと感じました。
正面入口を入ると「ボランティアガイド」の看板がありましたが、あいにく出払った後のようでした。そのとき「わたしたち近くの栗林小学校6年生です。」と数人の児童が声を掛けてくれました。「よろしかったら、私たちが約50分間ご案内いたしますがいかがでしょうか?」と庭園案内をかってでてくれました!
レンタルサイクルの次の写真が、赤松と黒松の道。葉の見分け方を説明してくれました。小学生達はガイド中もメモを見ながら、中には丸暗記している児童までいて一生懸命に庭園ガイドをしっかりと務めていただきました。上の写真中央は「根上り五葉松」です。以前「日本の原点シリーズ・木の文化3巻」新建新聞社発行で見たことがありましたが、実物は凄い。この壮大な松を見ながら南湖を回遊し、あっという間に1時間弱の庭園ガイドは終了しました。観光地のこうした大人のボランティアや地元の子供たちの世代を超えた地域の取り組みには、大変「心温まる」もてなしの心を感じ感動しました。何よりの思い出となりましたことに感謝しています。
一生懸命にガイドを務めてくれた地元「栗林小学校」の児童さんたち。どうもありがとう。
その後、わたしのお礼の手紙に対し、栗林小学校様からお手紙を頂戴いたしましたので抜粋にてご紹介させていただきます!
「本校では、6年生での総合的な学習の時間において「語ろう!栗林の文化を支える人の心を」というテーマのもと、先人の築きあげてきた文化の素晴らしさを味わい、人々の思いを大切にしようとする児童の育成を目指し、日々の活動に取り組んでおります。ガイドグループの子供たちには、特別名勝「栗林公園」でのガイド体験を通して、自分達の住む地域の文化に誇りを持ち、地域の一員として自分たちも大切にしていこうという気持ちが育ってくれればと願いながら活動を進めています。・・・(中略)これからも活動を続け、地域の文化、日本の文化を大切にしようとする心を育てていきたいと思っております。・・・
高松市栗林小学校6年生担任一同
長い年月、多くの人達に受け継がれてきた文化遺産は、現在、地域社会で最も重要な教育関係者の努力を背景に地元の小学生達の社会教育の一環として授業での「庭園ガイドツアー」という形で伝承されていました。
―高松の新名所/旧北浜倉庫・北浜Alley―
北浜という地区が高松港にあります。かつては貨物や観光フェリーが岡山宇野港などと行き来する大きな物流拠点であったこの界隈は、老朽化や瀬戸大橋等の陸路開通とともに寂れつつありました。この北浜。わたしが小学4年(当時幼馴じみのお父さんが三越高松店開店で転居し家族で夏休みに訪れた)で初めて四国に来たときの印象ではフェ
リーの船着場からコンテナや倉庫や線路が見えた記憶がありました。大阪万博の頃の話ですから高度成長期の繁栄を経て、3〜40年間で激変してきたに違いないだろう。
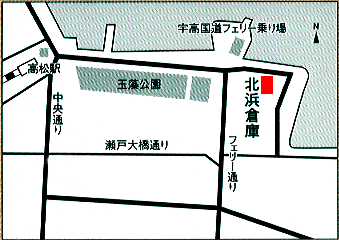
宇高連絡船からの北浜倉庫街。
5年ほど前、「若者中心の町興し」が始まっているとのNHK朝の報道で見たのを思い出
し、仲間数人で出かけてみました。錆びた倉庫の壁や今にも落ちそうな老練な屋根の一角。外見はほぼそのままで、そこを改装しパブ、レストラン、雑貨や、美容室と若者向けの店舗になっています。「黒船屋」さんは約70年前の穀物倉庫を改装したパブレストラン。2階にある。マスターの溝土慶造さんは、大学以来、長崎から高松に移住された、きさくで話し易い方でした。吹き抜けの2階は回廊で1階はマスターの友人が経営される美容室が見渡せる。どちらも中はオシャレに改装され、倉庫だった天井のトラス梁や束、土壁もそのままでありながら、照明の演出や店舗装飾ですっかり改装され気持ちの良い場所となっています。ヨーロッパに見られる古い建物でありながら中は一変して現代にマッチする設えという感じでしょうか。近年、古いものを捨て去り、新しいものが一番という考えとは違う、古いものを長く使い、簡単に壊さず社会資本として価値を置くヨーロッパに近い改装でしょうか?
.jpg)
まさに、リモデル!という雰囲気のお店でした。「阪神淡路大震災でここの壁が割れ、このあいだの台風9号でここから雨漏りして・・・」とオーナーの溝土さんの言うとおり、建物自体が過去の有事を物語っていました。なぜ大手開発事業者が入らなかったのだろうか?「地権者や住民がおり町の鎮守様を守る気風がかなり影響したようです。北浜も、西浜も同じように鎮守がありますからね。たまたま簡単に壊せず残ったんですよ。」と溝土さんは言う。翌早朝、高松駅に向かう途中港守りの神社があるのを見ました。この「北浜地区」の「黒船屋さん」、お店の雰囲気も、料理も美味ですよ。皆さんも高松の新名所「北浜地区」に是非一度お出かけください。
黒舟屋さんの店内、オーナーの溝土さん親子と。

―栃木・足利市で現在、民家再生中―
静かな農村地帯に昔懐かしい風情を残す村「岩木邸」は江戸時代には、この土地で栄えていた名主。現在、県道沿いに立つこの家の母屋は約120年前のもの。昔は街道の両脇に茅葺屋根の家々が立ち並ぶ日本の原風景を残す土地でもあった。最近はテレビの番組でも多く登場するようになった古民家とはいえ、子供の頃には「暗くて寒くて怖い」場所と思い育ったそうです。しかし年を重ねるうちに、いつしか何ともいえない愛着が沸き起こり始めたと言う岩木さん。今年から再生を少しづつ始められました。「あと100年使い続ける」と。これは、まさに「200年住宅」の真髄ではないでしょうか?新築したら何もしないで200年耐用するというものではなく、定期的に愛着を持ち、次代を越えメンテナンスしながら大切に使い住み続ける社会の実現が200年住宅の意味するところではないでしょうか?
屋敷の外観は黒漆喰塗り、内部は漆喰。当時の高位が覗える。
Before⇒After 座敷〜台所
↓ ↓ ↓
Before⇒After 布団部屋〜居間 居間に新しい柱を入れ建具で仕切る。天井は弁柄、自然塗料、床は福島桐を使用。
古民家では、歴史文化的な背景を知ることで、ものの真の価値を知ることが出来ます。裏付けある知識を持つことで「先人たちの知恵」のルーツを知ることが出来ます。それらを正しく知ることで、またその知恵をより活用するという長い年月をかけ熟成されてきたし、先人達の知恵を尊び、スローフード、スローライフの精神が芽生えてきたのだと思います。
 「エコの先端をいく文化を取り戻す」ビンテージリフォーム
「エコの先端をいく文化を取り戻す」ビンテージリフォーム
江戸時代から、木材を再利用するのは当り前の時代でした。これがいつしか捨てる文化に変わってしまった。究極のエコロジーは、そのままの形で出来るだけ長く使うこと。ビンテージリフォームは、そんな私達の考えが詰まったコンセプト・リフォームです!リフォームアップルで強力に推進中!
古材を多用するビンテージリフォームは、高い志と古来の伝統工法の豊富な見識を習得した古材施工技術士に是非一度ご相談下さい。
|
===大切なものを壊さない。使い継ぎ再生させる。===福島県会津から古材を入荷しました。=== |
| 民家再生トップへ戻る |

.jpg)