「明治・大正・昭和初期の文化人の街並みを歩こう。ロマネスクな風景が残る町」
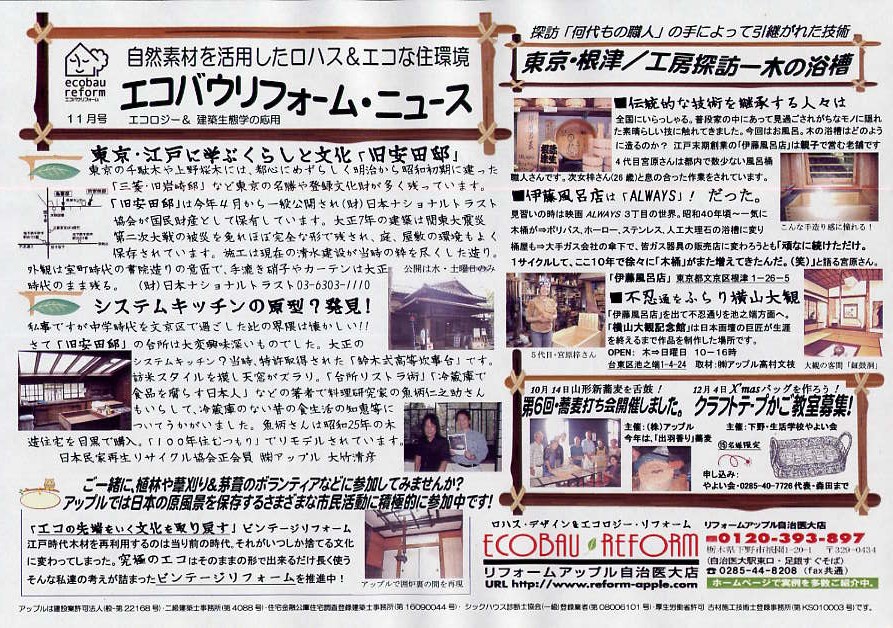
東京・千駄木「旧安田邸」
文京区千駄木にある大正の近代和風建築として、東京都名勝として今年4月から一般公開されています。財団法人日本ナショナルトラスト協会は、この安田邸を国民財産として保有しています。大正7年に建てられ関東大震災と第二次世界大戦の被災を免れほぼ完全な形で残され、庭を含めた屋敷の環境がよく保存されていました。安田邸は「豊島園」の創始者で実業家の藤田好三郎氏が大正8年に建てたものを大正12年、旧安田財閥の創始者安田善次郎の女婿・善四郎が買い取ったもの。施工は現在の清水建設が当時の粋を尽くし、当時は珍しく高価であった国産「栂つが材」を多用しています。外観は室町時代の書院造りの意匠の「鵜形」、内部建築は、和室は備後たたみを敷き詰め、建具の組子は全て面取り漆の額、玄関の格天井など贅沢なつくり。洋室で居間の造作材は栂ではなく「胡桃」をつかい、大正手漉きガラスやカーテンも大正8年のものがそのまま残る。台所が大変興味深いものでした。大正時代のシステムキッチン?「鈴木式高等炊事台」と呼ばれ特許取得されていた当時のシステムキッチン。天窓がズラリと取られ、訪米のスタイルを模したもの。床下収納は深く1メートルとどあるようで、収納棚も当時としては画期的なものだっただろう。
魚柄仁之助さんのお話
見学が終わり、後半は2階の客まで魚柄仁之助さんの講話をうかがう機会がありました。魚柄仁之助は「100年住むつもり」で購入された昭和25年の木造住宅をお持ちで、改築されています。この「100年住むつもりで改築」の住宅は目黒で2400万円と本人曰く格安?で購入し、1500万円掛けてリモデルしています。これから日本は「これを直してくれた大工のおじさんの技術に対して1万円を払うという経済」に替えるべきだと言います。
日本は、関東大震災以降、薪、かまどという生活からガスに替わり、大正後期~昭和初期に火力のあるガスで中華料理が入ったそうです。資源のない日本は今、原発をエネルギーのもととするオール電化に移行しようとしているが、大きな間違いを犯しかねないと語られました。明治以前は日本には石化燃料はない循環型社会であった。石化燃料は掘り出したら最後それでおしまい。プルトニウムは時代に大量の使用済み核燃料という膨大
な負の遺産を次代に残す。今後、日本人の暮らしには、経済的にも規模的にもスケールダウンが必要とおっしゃっります。
100年住むために
魚柄仁之助さんは、痛んだ根太をジャッキアップし総入替されています。梁も後から入れ込んでいます。室内の電線は碍子で結んでいます。私たちが使うFケーブルは「ねずみ」が齧り漏電することがアル。そのための碍子で露出配線という訳ではありませんが、昔の土壁と言うのは、今みたいに壁裏は空洞ではない。土壁の中には「竹コマイ」で編んだ密な構造があり隙間無く「土」が塗りこまれているから「電線」が通せないわけ。魚柄さんは「料理研究か」ですから「ねずみ」は禁物と言うことで「天井」は全部取り払いました。屋上では「干物」を干したり「昼寝」するために重要な場所。電灯のカバーは以前の「古道具屋」時代の在庫品。古いものが好きなわけではなく、バブルの時代に、田園調布など地上げが凄まじく家財が処分しなければならない人がいる一方で、儲けた人たちが「レトロ」とかいい、古いものを買っていく。東京の人には捨てるために「金を払い」捨てられるようなものに「高価」な金額を払い大事に使う人もいる。この両方を結びつけた運動ではなく商売を魚柄さんはやっていた。魚柄さんの家には「合板の家具」はありません。昔の古いものには探してもないから。洋間のテーブルは自作ですが、古道具や時代の在庫品に手を加えた自作。いまは「キッチンスタジオ」として使う昭和25年のこの家も、撮影など無くなったらもっとこじんまりと改築するそうです。大型冷蔵庫が入り、日本の食生活はかわった。それ以前伝えられた食べ物の「保存技術」を失ってしまった。お話を2時間近く伺っていても時間があっという間に過ぎた。何を豊かだと思うのか?個人の自由には違いがありませんが、その豊かさの定義が大事だと考えさせられる講話でした。豊かに生きることとは・・・
東京・千駄木「旧安田邸」の詳しいレポートと写真は
東京・根津「伊藤風呂店」
伝統的な技術を継承する人々は多くはありませんが、まだ全国にいらっしゃいます。今回は、以前はどこの家の中にあったもが、長年見過ごされてしまったモノ。そんな懐かしさの中に、隠れた素晴らしい技に触れてきました。今回はお風呂。木の浴槽はどのように造るのだろうか? 長年の疑問でした。江戸末期創業の「伊藤風呂店」は親子で営む老舗です。4代目宮原さん(57才)は都内で数少ない風呂桶職人さんです。次女梓さん(26歳)と息の合った作業を今もされています。4代目が始めた見習い頃の伊藤風呂店はまるで映画「ALWAYS」! だったそうです。初めて数年たった昭和40年頃~一気に木桶は、ポリバス、ホーロー、ステンレス、人工大理石の浴槽に急変したそうです。当然当時の桶屋も、大手ガス会社の傘下に入り、皆ガス器具の販売店に変わたそうです。そのような時代に逆らったのはうちだけで「頑なに続けただけ。1サイクルして、ここ10年で徐々に「木桶」がまた増えてきたんだよ。(笑)」と語る4代目宮原さん。5代目の梓さんはまだまだ、修行中で風呂桶は作らないそうですが、自作の手桶は見事に繊細な技を感じさせてくれました。 「伊藤風呂店」東京都文京区根津1-26-5
不忍通をふらり横山大観 台東区池之端1-4-24 OPEN: 木⇒日曜日 10-16時
「伊藤風呂店」を出て不忍通りを池之端方面へ。「横山大観記念館」が見えてきます。ここは日本画壇の巨匠が生涯を終えるまで作品を制作した場所です。 取材:㈱アップル高村文枝

 「エコの先端をいく文化を取り戻す」 ビンテージリフォーム
「エコの先端をいく文化を取り戻す」 ビンテージリフォーム